目次
体液量バランス異常リスク状態(看護計画)
いつもご覧いただきありがとうございます。
今回は「体液量バランス異常リスク状態」について考えていきます。血管内液・組織間液・細胞内液が、減少、増加するために、健康を損なうおそれのある状態に対して介入していきます。
以前に、「電解質バランス異常リスク状態」についても記事をアップしました。リンクを貼っていますので気になる方はご覧ください。
今回は、細胞内外も含む「体液」に焦点を当てていきます。
体液といった広範囲を対象としますので、概論(体液とは何か、体液バランスを崩してしまう原因は何か)のみを取り扱うこととします。
体液バランス異常となる原因(疾患・病態)はいくつもありますので、いずれ症状別の看護計画をアップしていくときにリンクを張る形にしたいとおもいます。
では、体液とは何だったかというおさらいから始めていきましょう。
お急ぎの方は下のジャンプから移動してください。
下の関連の計画も参考にしてみてください。
1.体液バランスとは
1)体液とは
動物が何らかの形で体内に持っている液体のこと。
一般的には消化液(唾液、胃液、胆汁、膵液、腸液)、汗、涙、鼻汁、尿、精液、用水、乳汁も体液といわれるが、今回はこれらを含まず、生物学的な体液を「体液」とする。
生物学的には、管腔内、組織間(管腔外)、体腔内、に存在する液体をさす。
1.細胞内液
2.細胞外液
(1)管内液
①血漿
②リンパ液
(2)管外液
①間質液 ※1
(3)その他体腔液
①漿膜腔液・・・胸水、腹水、心嚢液
②脳脊髄液
③関節液(滑液)
④眼房水(房水)
※1 間質液
間質液とは、細胞を浸す液体で、細胞外液より血液とリンパ液を除く体液を指す。
組織液ともよばれる。
酸素やタンパク質は、血管→毛細血管→間質液→細胞へと拡散する。
海外ではリンパ液と間質液の明確な区別がなく、「リンパ液」とだけ呼ばれる。
間質液は血管膜(半透膜)を通して、膠質浸透圧や筋肉などの圧力によって、水分と血液ガス(酸素と二酸化炭素)をやり取りする。
タンパク質や老廃物、ウィルスや癌細胞などの分子の大きいものはリンパ管を通る。
2)体液の構成
(1)成人の場合
・全体液は体重の60%
↓内訳は
・細胞内液が40%
・細胞外液が20%
・間質液が15%
・血液(血漿成分のみ)とリンパ液 あわせてが4.5%
・体腔液が0.5%
体重70kg男性を例に、具体的な数字で見てみると、、、
・全水分量:42L
・細胞内液:28L(42L×40%÷60%)
・細胞外液:14L(42L×20%÷60%)
・血漿+リンパ液:3.15L(42L×4.5%÷60%)
・間質液10.5L(42L×15%÷60%)
3)年齢層による構成の違い
・成人女性は男性に比べて脂肪が多いため、体重に対する体液の比率が小さくなる(男性の8割ほど)。
・新生児は体液比が最も高い:78%(細胞外液が多い)
※4歳ごろに成人と同レベルになる
・高齢者は体液比が低い:50%(細胞内液の減少)
4)体液の移動
①細胞の内側と外側の水移動は浸透圧による。
細胞の内側と外側はイオンとタンパク分子の移動が起こらない。
そのため、細胞外に低張の補液がなされると、浸透圧格差で細胞外から細胞内へ水分が移動する。
②血管の内側と外側は浸透圧が同じ。
血管の内側と外側はイオンの移動が原則自由なため浸透圧はほぼ等しくなる。
血管を通過できない低たんぱく分子などでつくられる膠質浸透圧格差により水移動が行われる。
5)日々の水分出納
(1)摂取する水分
①飲料水 1100ml
②食物中の水 1000ml
③代謝水 300ml
合計 2400ml
※代謝水は、栄養素が体内で代謝されて発生する水
(2)1日に排泄する水分
①尿
・随意尿: 1000ml
・不可避尿:400ml
②不感蒸泄 900ml
③便 100ml
合計 2400ml
2.「体液量バランス異常リスク状態」看護計画の対象
1)細胞外液の増加
①腎疾患(水・Naの排泄が困難となる)
・ネフローゼ症候群
・腎不全
②心不全
・循環不全
・浮腫
③水中毒
・抗精神病薬の副作用
④肝硬変
⑤内分泌異常
・原発性アルドステロン症
⑥その他
・過剰輸液・輸液
・妊娠
2)細胞外液の減少
①脱水
・低張性(ナトリウム欠乏性):熱傷、利尿薬、アジソン病(副腎皮質機能低下症)、嘔吐、下痢、不適切輸液
※細胞内に水が移行するため、細胞外液が著明に減少する。ナトリウムを多く喪失するため
低張性の脱水と言われる
・等張性(混合性):熱傷、出血、下痢
※急速に細胞外液を喪失する状態のとき、細胞外液そのものが消失=等張性のものが喪失するため
等張性の脱水と言われる
・高張性(水欠乏性):発熱、発汗過多、下痢、急性腎不全回復期、尿崩症
※ナトリウムより水分を多く喪失し、細胞内液から水分が細胞外液へ移動する。体液全体が濃縮
した状態となっているとき高張性脱水と言われる
②出血
・外傷
・手術
・コンパートメント症候群
③消化器系
・嘔吐
・下痢
④内分泌異常
・糖尿病
・高浸透圧性脱水
・浸透圧利尿(尿から糖が出る)
⑤特定の薬剤の使用
・利尿剤(ループ利尿薬・サイアザイド系利尿薬)
・マンニトール
・アルブミン製剤
⑥腎臓疾患
・急性腎不全の利尿期
・間質性腎炎
⑦皮膚
・熱傷
・大量発汗
⑧浮腫をきたす病態
・低たんぱく血症
ここまでご覧いただきありがとうございました。
体液量の増加・減少は原疾患に対する治療と看護になるので、いずれ疾患別・症状別の看護計画をアップするときにリンクを貼っていきます。
電解質バランス異常リスク状態
下痢
嚥下障害
非効果的健康自主管理

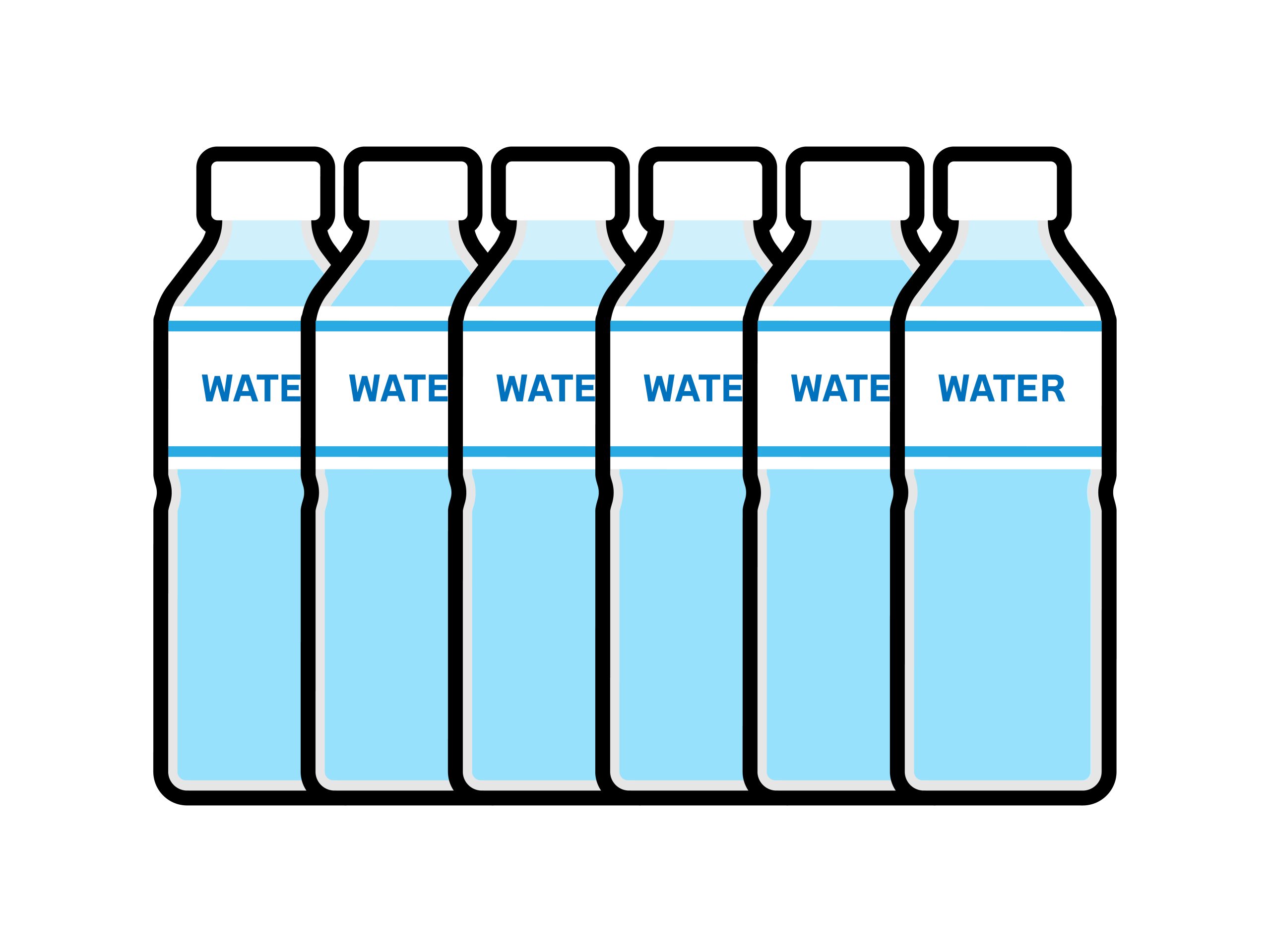
[…] 体液量バランス異常リスク状態(看護計画) […]
[…] 体液量バランス異常リスク状態(看護計画) […]