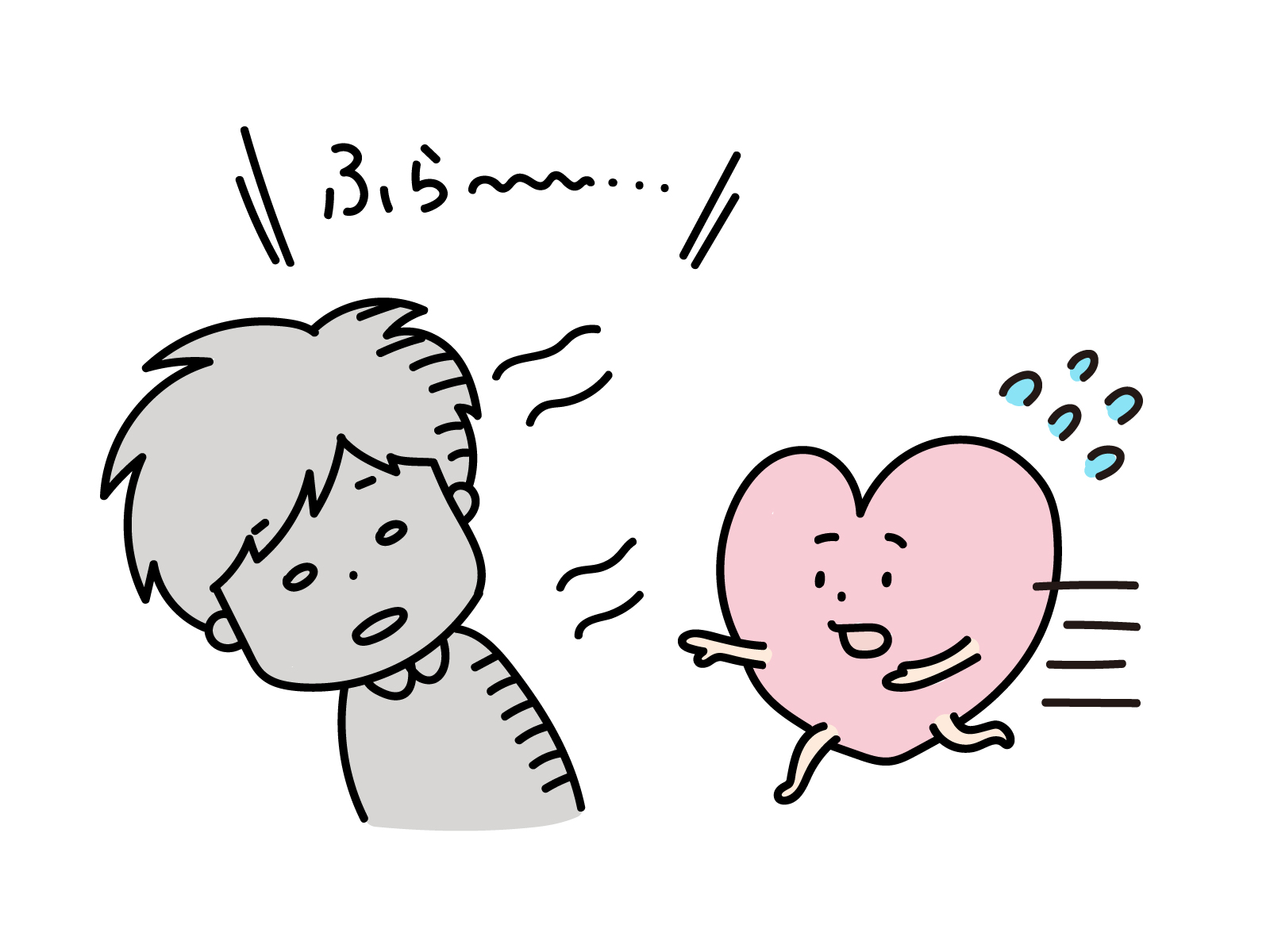目次
非効果的防御力(看護計画)
いつもご覧いただきありがとうございます。
今回は「非効果的防御力」について考えていきます。
この診断は、病気やケガに対する「防御力」が十分でない方を対象に立案していきます
具体的には免疫不全、凝固系異常、全身状態の悪化などを対象にするようですが、NANDAの診断指標や関連因子を見ると、もっと広範囲を対象にするようにも見えます。たとえば、高齢による心身の虚弱や精神疾患も含まれるような、、、。
立案する際には、他の「感染リスク状態」などのように具体的な診断で立案できる場合にはその方がよいでしょう。
「非効果的防御力」を立案するにしても、診断指標に合致していれば間違いと言うことはないと思いますので、その診断に至るまでの根拠が明確に述べられれば良いのではないでしょうか。
こんなケースはどうかな?と疑問に思った場合は、私も一緒に考えますので、一番下のコメント欄から意見をお寄せ下さい。
前置きが長くなってしまいましたが、一緒に考えていきましょう!
まずは防御力について考えていきましょう
お急ぎの方は下のジャンプより目的位置に移動してください。
類似の計画はこの記事の最後に紹介しています。こちらからジャンプ
1.防御力(≒抵抗力)
防御力・抵抗力とはなんでしょうか?
防御力が十分な状態とは「心身ともに健康な状態」と考えます。
それは、病気を寄せ付けず(免疫系が正常に機能している)、栄養状態もよく、悪性腫瘍や内臓疾患などの病気に抵抗する力があり、かりに病気にかかったとしても回復させる力を備えている、次のような状態と言えるのではないでしょうか。
1)抵抗力のある状態
・十分に栄養を摂取しており、年齢に応じた体格である。
・BMIが正常値である
・意識がはっきりしている
・健康管理ができる
・精神的に安定している
・活気がある
・一時的な体力がある(急性疾患を乗り越える体力がある)
・長期的な体力がある(慢性疾患を悪化させない体力がある)
・若さがある(回復力が高い)
・免疫力が高い(病原菌に対抗する力がある)(不良細胞を貪食する能力があり、体内を正常に導く力がある)
全てにおいて十分な人は少ないと思います。投薬などをしながらでも、健康を維持していて、ある程度余力があれば抵抗力があると言えるのではないでしょうか。
では、抵抗力が低下した状態とはどのような状態でしょうか、考えてみます。
2)抵抗力が弱った状態
・高齢
・若年(乳幼児)
・るいそう、栄養不良
・筋力、体力不足
・消耗性疾患
・免疫力低下を来す疾患
・免疫力低下をきたす治療
・外傷、失血
これらが上げられると思います。疾患や治療は挙げるとかなりの数になります。
具体的に次で紹介していきます。
2.抵抗力を低下させる疾患や治療
1)抵抗力を低下させる疾患
・糖尿病
・呼吸不全
・悪性腫瘍
・腎不全
・心不全
・肝不全など
2)免疫力低下を来す疾患
・免疫不全症候群:
体液性免疫や細胞性免疫の機能不全による抵抗力減弱をきたす疾患群。先天性と後天性がある。
・先天性:
無γグロブリン血症、IgA欠損症、補体欠損症、ディジョージ症候群(胸腺形成不全)、慢性肉芽腫症
・後天性:
自己免疫疾患、リンパ系悪性腫瘍、ウィルス疾患(HIVなど)
3)免疫力低下をきたす治療
・手術
・侵襲的治療
・放射線治療
・免疫抑制薬、抗がん剤
・副腎皮質ステロイド:抗原提示細胞・リンパ球機能を抑制
・特異的免疫抑制剤:リンパ球のサイトカイン産生を抑制
(シクロスポリン、タクロリムス、デオキシスパーガリン)
・細胞毒性薬:核酸合成阻害
(シクロフォスファミド、メトトレキサート、アザチオプリン)
・分子標的薬:免疫応答のステップに存在する細胞を標的とする。
(標的は、膜抗原・受容体・接着因子・サイトカインなど)
3.非効果的防御力の適応
・高齢
・若年(乳幼児)
・るいそう、栄養不良
・筋力、体力不足
・外傷、失血
・免疫力低下を来す疾患
・糖尿病
・呼吸不全
・悪性腫瘍
・腎不全
・心不全
・肝不全
・無γグロブリン血症
・IgA欠損症、補体欠損症
・ディジョージ症候群(胸腺形成不全)
・慢性肉芽腫症
・自己免疫疾患
・リンパ系悪性腫瘍
・ウィルス疾患(HIVなど)、
・免疫力低下をきたす治療
・手術
・侵襲的治療
・放射線治療
・免疫抑制薬、抗がん剤
・副腎皮質ステロイド
・特異的免疫抑制剤
・細胞毒性薬
・分子標的薬
4.目標設定
目標は患者さんを主語にして立てます。
・活動と休息のリズムを整えることができる。
・十分な栄養を摂取できる。
・適度な気分転換ができる。
・服薬管理ができる。
・適度な運動を取り入れることができる。
・感染症流行時には感染予防対策をとることができる。
看護師を主語にする場合にはつぎのようになるとおもいます。
・患者と家族が、抵抗力が十分でないことを理解し、感染予防や症状悪化を回避するための方法を習得できるように支援する。
・患者と家族が、抵抗力低下を防ぐ、体力維持増強のための方法(食事・運動)を習得できるように支援する。
・病態、ADLに合わせた介助を行う。
・不快症状を緩和し、安全・安心に療養生活を送るように調整する。
5.看護計画
1)観察計画《OP》
・年齢(高齢、若年)
・疾患、疾患の家族歴、病期
・症状、バイタルサイン
・疲労、慢性疲労
・感染徴候(発熱、発赤、腫脹、疼痛)、繰り返す感染、遷延する感染
・恐怖を感じる症状(幻覚、呼吸苦、胸痛など)
・不快症状(頭痛、疼痛、嘔気、下痢など)
・治療の環境(一般症、感染症病床、ICU、クリーンルームなど)
・家族構成
・自己管理可能かどうか
・認知力(長谷川式20点以下、MMSE21点以下で認知症疑い)
・精神状態
・意識レベル
・活動量、安静度、ADL
・栄養状態
・体重・BMI・体重減少率
・摂食量、摂食内容
・嚥下機能低下、誤嚥、
・摂食量低下(う歯、嚥下機能低下)
・食欲低下(意識レベル、精神疾患、疼痛など)
・下痢、消化器系疾患で吸収に問題あり
・血液データ:
TP(6.7~8.3)、Alb(3.8~5.3)、総コレステロール(210~210)、貧血Hb(12~17)
・免疫能
・胃腸機能、呼吸機能、泌尿生殖器の機能
・抗体価
・皮膚の統合性、粘膜の統合性
・検査値
・白血球、T4・T8細胞値、補体価
・治療
・手術
・侵襲的治療
・抗がん剤、免疫抑制剤、ステロイド
・コンプライアンス
・自身の疾患の経過を理解しているか
・自身の疾患に伴う感染リスクを理解しているか
・自身の疾患に伴う心身を悪化させるリスクを理解しているか。
・嗜好:喫煙、飲酒など
・リスクを回避するための方法を理解しているか
・感染リスクを回避するための方法を理解しているか
・予防接種の必要性を理解し、接種しているか(アレルギーのある場合はのぞく)
・回復を促進する生活習慣について理解しているか
・治療計画に同意し自己管理できているか
(内服、吸入、食事、運動など)
・治療計画通りに自己管理できていない(自己中断・拒薬など)
・家族の理解、介護
・使用している社会資源
2)行動計画《TP》
・症状を悪化させる因子を排除する。
・感染を予防するための手洗いとマスク着用をする(患者・家族も、医療者も)。
・無菌室への入室は、入室基準を守り手順通りに行う。
・口内炎で食事が進まないなどの理由がある場合には、一時的に食形態を変更する(ムース食やゼリーなど)
・無菌室への食品の持ち込みは、病院の基準に適合したものでなくてはならないため、患者や家族が持ち込む前に確認する。(生もの・半生・冷凍・はちみつはNG。レトルトなどの密閉されたもの・缶詰・カップ麺はOKなど病院基準と照らして確認する)
・十分に休息が取れるように環境整備を行う。(照明、音、においなど)
・安静度を守れるように巡視や見守りを行う。
・活動と休息のバランスが整うようケアの計画を立てる。
・適度に運動をしてもらえるように声かけや見守りを行う。
・リハビリと情報共有し、患者のADLに合わせた介助を行う。
(廊下歩行、トイレ歩行、杖歩行、歩行器介助、ベッド周囲、ポータブルトイレなど)
・疼痛や嘔気、下痢などの不快症状のある場合には、医師に対処してもらえるよう報告・相談する。
・鎮痛剤など頓服で処方されている場合には、必要に応じて使用する。
3)教育計画《EP》
・定期的に受診するよう説明する。内服を切らさない、症状の変化を診てもらう為に必要。
・勧められている予防接種は受けるように説明する(アレルギーや医師の許可のない場合は除く)
・症状を悪化させる因子を排除するように説明する。
・感染を予防するための手洗いとマスク着用の必要性を説明する(患者・家族も、医療者も)。
・無菌室への入室は、入室基準を守り手順通りに行っていただくよう、パンフレットなどを用いて説明する。
・無菌室への食品の持ち込みは、病院の基準に適合したものでなくてはならないため、患者や家族が持ち込む前に確認する。(生もの・半生・冷凍・はちみつはNG。レトルトなどの密閉されたもの・缶詰・カップ麺はOKなど病院基準と照らして確認する)
・十分に休息が取れるように環境整備を行う。(照明、音、においなど)
・安静度を守れるように巡視や見守りを行う。
・適度に栄養摂取できるよう勧める。
・適度に運動をするように勧める。(寝たきり予防・フレイル予防)
・患者、リハビリ職と情報共有し、患者のADLに合わせた介助を行う。
(廊下歩行、トイレ歩行、杖歩行、歩行器介助、ベッド周囲、ポータブルトイレなど)
・在宅療養に向けて、メディカルソーシャルワーカーと連携し、療養生活に必要な環境が整うように調整する。
★類似の計画
感染リスク状態
高齢者虚弱シンドローム
非効果的健康自主管理
非効果的健康維持行動